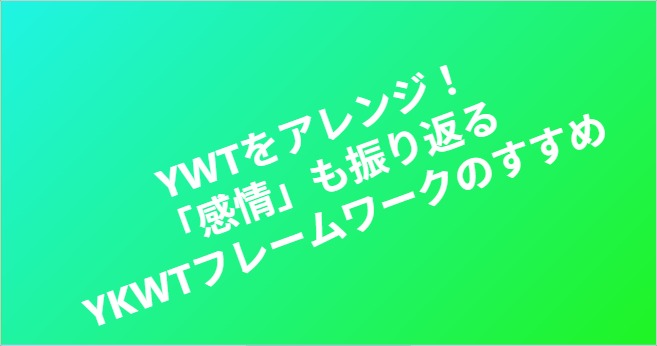YWTをアレンジ!「感情」も振り返るYKWTフレームワークのすすめ
『振り返りが大事』とわかっていても、『何を書けばいいの?』『ただの日記で終わってしまう…』と感じていませんか?振り返りを『義務』から『成長を加速させる強力なツール』に変えてみませんか?
まずおすすめするのが、「YWT」というシンプルなフレームワークです。 今回は、そのYWTをアレンジして、「かんじたこと(Feeling)」の要素を加えた「YKWT」というアレンジ版の振り返り手法をご紹介します。
これを実践することで、思考が整理されるだけでなく、自分の感情にも向き合うことで、より深い学びに繋がります。
まずは基本の「YWT」から
YWTは、日本能率協会コンサルティング(JMAC)が開発した振り返り・リフレクション(内省)の考え方・実践手法です。
- Y = やったこと (Fact)
- W = わかったこと (Discovery)
- T = つぎにやること (Next Action)
この3つの視点で経験を整理します。 大きな特徴は、KPT法などで使われる「問題(Problem)」ではなく「わかったこと(Discovery)」という発見に焦点を当てる点です。これにより、反省だけでなく、自分の成長や新たな気づきといったポジティブな側面に光を当てやすく、未来志向で前向きな振り返りができると言われています。
Y:やったこと(事実)
まず、実際に「やったこと」を客観的な事実として書き出します。感情や評価は含めず、誰が見ても同じように認識できる行動をリストアップします。
例:
- 新しいプロジェクト管理ツールを導入した。
W:わかったこと(発見・学び)
次に、「やったこと」を通して、何に気づいたか、何を学んだかを書き出します。これは、うまくいったことだけでなく、「こうすればもっと良くなるかも」といった改善のヒントも含まれます。
例:
- (Yから →)ツールを導入したことで、チーム全体のタスクが見える化された。
T:つぎにやること(次の行動)
最後に、「わかったこと」を元に、次は何をするかを具体的に決めます。「もっと頑張る」のような曖昧な目標ではなく、「誰が」「いつまでに」「何をするか」がわかるレベルまで具体化するのがポイントです。
例:
- (Wから →)来週の月曜日までに、チームメンバー向けにツールの基本的な使い方を説明する会を開く。
参考:YWT(ワイ・ダブリュー・ティー)|JMAC(日本能率協会コンサルティング)
なぜ「感情」を加えることが良いのか?
YWTは非常に優れたフレームワークですが、「やったこと(事実)」から直接「わかったこと(学び)」を導き出そうとすると、少し難しく感じることがあります。
「事実」と「学び」の間にある、自分自身の「感情」に目を向けることで、振り返りはもっと深まります。 「なぜ楽しかったんだろう?」「なぜ焦ったんだろう?」と感情の背景を探ることで、表面的には見えてこなかった、自分だけの学びや価値観に気づくことができるのです。
そこで登場するのが「YKWT」
この「感情」の視点を加えたのが、「YKWT」です。
YKWTは、4つの要素の頭文字をとった言葉です。
- Y = やったこと (Fact)
- K = かんじたこと (Feeling)
- W = わかったこと (Discovery)
- T = つぎにやること (Next Action)
「やったこと」という事実と、「わかったこと」という学びの間に、「かんじたこと」を挟むのが大きなポイントです。事実と学びを感情でつなぐことで、より深く自分事として振り返りができるのです。
Y:やったこと(事実)
ここでは、実際に「やったこと」を客観的に、淡々と書き出します。 「〇〇の資料を作成した」「△△の会議に参加した」というように、評価や感情を入れずに、事実だけをリストアップするのがポイントです。
例:
- 新しいプロジェクト管理ツールを導入した。
- クライアントとの定例ミーティングで、新機能のデモを行った。
K:かんじたこと(感情)
次に、「Y:やったこと」に対して、そのとき自分がどう感じたかを書き出します。 「楽しかった」「悔しかった」「もっとうまくできたはず」「これは意外と簡単だった」といった感情は、次の「わかったこと」を見つけるための大きなヒントになります。
例:
- (Y: ツール導入 →)思ったより初期設定に時間がかかったけど、チームのタスクが可視化されて安心感が生まれた。
- (Y: デモ実施 →)デモの途中で〇〇という質問を受けて、少し焦った。
W:わかったこと(発見・学び)
ここがYKWTの肝となる部分です。 「Y:やったこと」に対して「なぜKのように感じたのか?」と自問自答することで、学びを掘り下げます。事実と感情の背景を探ることで、自分だけのオリジナルな発見が生まれます。
例:
- (YとKから →)タスクの可視化は、チームの精神的な安定に繋がることがわかった。
- (YとKから →)自分では当たり前だと思っていた部分が、相手には伝わりにくいポイントだったとわかった。「焦り」を感じたのは、想定外の質問だったからだ。
T:つぎにやること(次の行動)
最後に、「W:わかったこと」から導き出される、具体的な次のアクションを決めます。 「頑張る」みたいな曖昧な目標ではなく、「〇〇の機能について、来週火曜日までにマニュアルを作る」といった、具体的で小さな一歩を書き出すのがコツです。
例:
- (W: 精神的な安定に繋がる →)ツールの使い方について、チーム内で共有会を開く。
- (W: 伝わりにくいポイントだった →)次回の説明資料では、〇〇の部分の解説を手厚くする。想定問答集も用意しておく。
YKWTがもたらすメリット
YWTの「未来志向」な良さはそのままに、「K:かんじたこと」を加えることで、自分のモチベーションの源泉や、ストレスを感じるポイントが明確になり、自己理解が深まるというメリットがあります。
なぜそう感じたのか?を考えることで、行動の裏にある価値観や思考のクセに気づくきっかけにもなります。